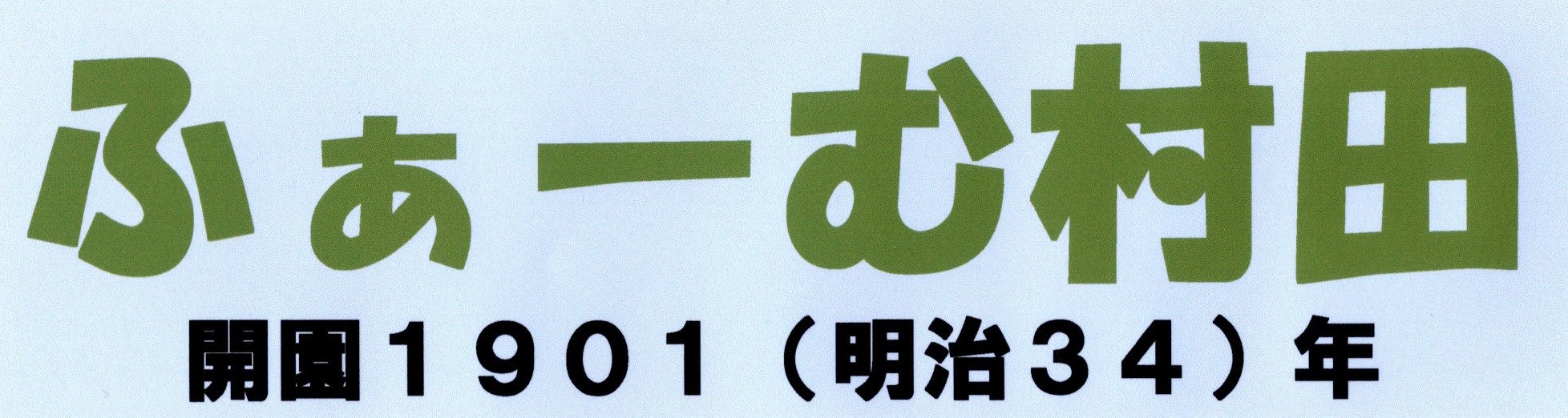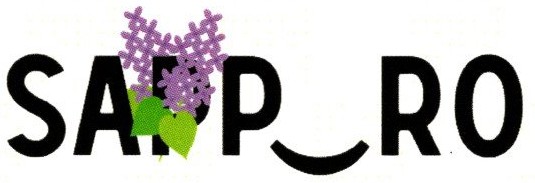- 1865(慶応元)年
- 開拓初代目「喜市」生まれる。
- 1886(明治19)年
- 琴似兵村に至る琴似新道(茨戸街道)と札幌に至る新琴似道路が完成する。
- 1887(明治20)年
- 九州氏族を中心に屯田兵146戸が第1陣として新琴似に入植する。
- 兵村の守護神として、中隊本部脇の湧き水の場所に三神を奉る祠を設ける。
- 私立新琴似小学校創立される。
- 屯田兵に種子は、麻、大麦、小麦、大豆、小豆、じゃがいもと蚕卵用原紙(養蚕が始まる)が給与される。
- ※明治20年代
- 開拓初代「喜市」札幌新琴似に入植し、開拓を始める。
- 1888(明治21)年
- 屯田兵74戸が第2陣として新琴似に入植する。
- 1890(明治23)年
- 北海道製麻会社(のちの帝国製麻)が現麻生町地域8千坪に亜麻製線工場を建設する(亜麻栽培が始まる)。
- 札幌製糖会社が設立(現札幌ファクとリー)され、砂糖の生産が始まり、ビート栽培が行われる。しかし、ビートの収量が少ないうえ、運搬費がかさんでいた。
- 安春川(人工排水溝)の開削始まる。
- 新琴似屯田兵中隊長:安藤貞一朗大尉が換金作物として、だいこん種子2合を各戸に配布し、耕作を奨励、耕作地が年々増加する。
- 新琴似中隊本部襲撃事件が発生、6人を処分する。
- 1891(明治24)年
- 夜盗虫の大発生で農作物が全滅する。
- 1892(明治25)年
- 稲作とエン麦の作付けを開始する。
- 寒冷地のために蚕の生育が悪く、個人の養蚕をやめる。
- 1893(明治26)年
- 新琴似小学校が私立から公立となる。
- だいこん栽培が、篠路や新琴似で多く栽培されるようになる。
- 1894(明治27)年
- 開拓2代目「勇」美唄で生まれる。
- 1895(明治28)年
- 第一大隊を解散し、新琴似屯田兵は後備役に編入、日清戦争に出征する。
- 稲作(たこ足直播)は江頭庄三郎が育成した品種「坊主」で栽培が広がる(昭和6~10年の冷害で、たこ足直播の栽培から、移植栽培へ)。
- 1896(明治29)年
- 屯田兵司令部が廃止され新琴似屯田兵は第七師団の直轄となる。
- 浄土真宗の新琴似説教所(現覚王寺)が開設する。
- 札幌製糖会社での砂糖生産が中止され、ビート栽培がされなくなる。
- 1897(明治30)年
- 屯田兵被服庫を仮遥拝所とし、毎年5月20日(開拓記念日)例大祭とした(現新琴似神社)。
- 座長:田中松次郎を中心に新琴似歌舞伎が旗揚げする。
- 新琴似農話会結成し洋式農業導入を図る。
- 新琴似だいこんを札幌に初出荷する。
- 1898(明治31)年
- 大洪水で、篠路だいこんが再起不能の打撃を受け、その後、新琴似だいこんがだいこん栽培の中心となる。
- 1901(明治34)年
- 新琴似巡査駐在所が設置される。
- 開拓初代「喜市」が屯田兵の坂本氏の給与地を含め、多数の人から土地を譲り受ける(現ふぁーむ村田の農園を取得)。
- 1902(明治35)年
- 開拓2代目「勇」村田家に養子に入る。
- 開拓2代目「勇」新琴似歌舞伎に参加する。
- 1903(明治36)年
- 害虫の大発生で農業被害を受ける。
- 1904(明治37)年
- 日露戦争に81人が出征する。
- 開拓初代「喜市」が新琴似で初めて物置で、新琴似だいこんを用いて漬物(たくあん)を漬け、販売する。
- 1905(明治38)年
- 新琴似郵便局が開局される。
- 1909(明治42)年
- 購販会を設立し、陸軍糧秣廠にエン麦を納入する。
- 1910(明治43)年
- 新琴似歌舞伎の常設劇場「若松館」のこけら落とし。
- 1912(明治45)年
- 乳牛の飼育が始まる。
- 1916(大正5)年
- 新琴似歌舞伎 解散する。
- 1917(大正6)年
- 新琴似神社の創立許可が内務省より受ける。
- 開拓3代目:正喜 生まれる。
- 1918(大正7)年
- 稲作は凶作や洪水被害が相次ぎ、米づくり農家が激減する(242haから15ha)。
- 1920(大正9)年
- 新川の氾濫で水稲に被害を受ける。
- 1923(大正12)年
- 琴似村に一級町村制施行となる。
- 新琴似に電灯が点く。
- 開拓2代目「勇」新琴似歌舞伎の常設劇場「若松館」を買取り、移設し、新琴似で初めて、漬物工場を建設・稼働させる(関西、関東、樺太に移出。歩兵第25連隊指定工場となる)。
- 干ばつと虫害で大根に被害を受ける。
- 1924(大正13)年
- 新琴似短歌会が発足する。
-
-
- 1926(昭和元)年
- 安春川改修工事が始まる(住民労働奉仕)。
- 1934(昭和9)年
- 札沼線(桑園~当別)開通、国鉄新琴似駅が開業する(1日4往復)。
- 安春川改修工事が竣工され、新琴似の大地が地盤改良され農作物の生産量が飛躍的に向上する。
- 1936(昭和11)年
- 新琴似だいこんの栽培最盛期となる(年間生産量800万本:札幌の人口20万人の漬物を賄う)。
- 1938(昭和13)年
- 開拓4代目「征一」生まれる。
- 1942(昭和17)年
- 琴似村に町制が施行される。
- 1944(昭和19)年
- 新琴似四番通りを軍用道路として拡張する。
-
-
- 1945(昭和20)年
- 農地法の施行により26町歩の神社用地が小作人所有となる。
- 開拓2代目「勇」漬物工場を廃業する。
- 1947(昭和22)年
- 琴似町立新琴似中学校が設立される。
- 1955(昭和30)年
- 琴似町が札幌市と合併する。
- 開拓初代目「喜市」没する(90歳)。
- ※昭和30年代半ば
- 開拓2代目「勇」新琴似神社の神主となる。
- 1957(昭和32)年
- 北海道製麻琴似製線工場が閉鎖する(亜麻栽培の終焉)。
- 1960(昭和35)年
- 新琴似だいこんが生産激減となり、急激な人口増加にともない耕作地が住宅地化される。
- 1963(昭和38)年
- 開拓2代目「勇」没する(69歳)。
- 1964(昭和39)年
- 札幌市電鉄、新琴似駅前停留所を開設する。
- 1965(昭和40)年
- 開拓5代目:拓一 生まれる。
- 1974(昭和49)
- 札幌市が新琴似屯田兵中隊本部を有形文化財に指定する。
- 札幌市電鉄北線の廃止により、新琴似駅前停留所を閉鎖する。
- 1978(昭和53)年
- 札幌市地下鉄南北線の延伸により、麻生駅開設される。
- 1987(昭和62)年
- 開拓5代目「拓一」北海道改良普及員資格試験に合格する。
- 開拓5代目「拓一」中学教諭一級:理科、高等学校教諭二級:農業・理科の普通免許を取得する。
-
-
- 1993(平成5)年
- 新琴似歌舞伎伝承会が設立され、新琴似歌舞伎が復活される。
- 2007(平成19)年
- 開拓3代目「正喜」没する(90歳)。
- 開拓5代目「拓一」普及指導員(農業)資格試験に合格する。
- 2008(平成20)年
- 開拓4代目「征一」没する(69歳)。
- 2016(平成28)年
- 「新琴似村屯田兵村記録」が北海道指定有形文化財に指定される。
- 開拓5代目「拓一」札幌市立新琴似小学校の総合学習で新琴似だいこん栽培などの授業が始まる(食育授業の開始:5年生中心)。
-
- 2021(令和3)年
- 開拓5代目「拓一」札幌市中核農家として登録を受ける。
- 2022(令和4)年
- 開拓5代目「拓一」新琴似小学校で、[新琴似の農作物の歴史]の出前授業が始まる(3年生・5年生)。
- 2023(令和5)年
- 開拓5代目「拓一」札幌市立新川中央小学校の総合学習で食育に係わる授業が始まる(特別支援学級)。
- 開拓5代目「拓一」札幌市立新琴似小学校(すばる学級)、新川中央小学校(わかくさ学級)のハロウィーン用ジャンボかぼちゃでランタンづくりが始まる。
- 2024(令和6)年
- 新琴似歌舞伎が札幌市無形民族文化財に認定される。
- 開拓5代目「拓一」札幌市立新琴似南小学校の総合学習で新琴似だいこん栽培などの授業や[新琴似の農作物の歴史]出前授業が始まる(食育授業の開始:4年生)。
- 開拓5代目「拓一」札幌市立新琴似小学校の出前授業で「パティスリーブリスブリス」と一緒にパンケーキづくりが始まる(5年生)。
- 開拓5代目「拓一」福祉に興味をもち、農福連携技術支援者の認定を受ける。
- 2025(令和7)年
- 開拓5代目「拓一」札幌市立あいの里東小学校の出前授業で「パティスリーブリスブリス」と一緒にパンケーキづくりが始まる(特別支援学級)。